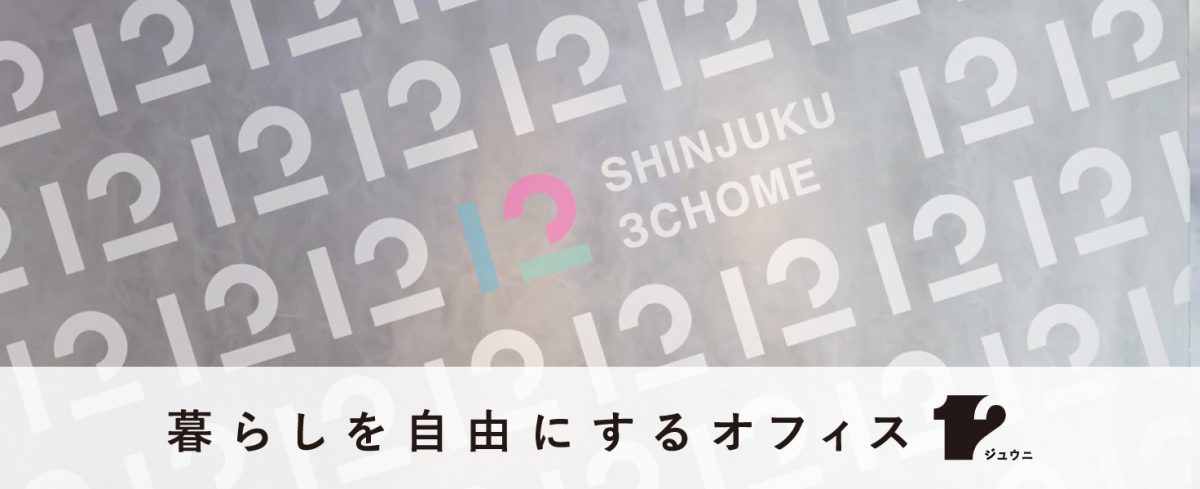永野 大輔さんインタビュー
次のアイデアを外から呼び込む「余白」の力 ~ソニーはなぜ銀座の一等地に公園を作ったのか
ソニー企業株式会社 代表取締役社長・チーフブランディングオフィサー。1992年にソニー株式会社入社。営業、マーケティング、経営戦略、CEO室などを経て2017年から現職。「Ginza Sony Park Project」のリーダーとして、2013年からプロジェクトを推進し続け、2018年8月9日に「Ginza Sony Park」をオープンさせた。
働くと暮らすが同居するさまざまな空間を訪問することで、これからのオフィスづくりや新しい働き方のヒントを探る、場のプロデューサー・横石崇の『しごとば探訪』。連載2回目の今回訪れたのは、Ginza Sony Park。ソニーはなぜ銀座の一等地に「公園」をつくったのか。「余白」を活かす空間デザインとそこに込められた狙いを、ソニー企業代表取締役社長でありチーフブランディングオフィサーの永野大輔さんに伺いました。
* 本記事は2020年2月に取材した内容を基に作成しております。施設の最新情報及び営業時間については、Ginza Sony Park 公式サイトにてご確認ください
2018年8月9日、解体された銀座 ソニービル跡地にできたのは、Ginza Sony Park(銀座ソニーパーク:以下ソニーパーク)という名の「公園」でした。銀座の一等地になぜ「公園」なのか。一私企業であるソニーがなぜ「公園」をつくるのか。さまざまな問いをぼくらにもたらしたソニーパークにはその後、今日に至る1年余りで560万人(2020年1月31日現在)が足を運んでいます。
今回はそんなソニーパークを運営するソニー企業株式会社 代表取締役社長 兼 チーフブランディングオフィサーの永野大輔さんに空間づくりについて、お話を伺いました。
実は、横石はソニーパークを作る過程で、少しだけお手伝いさせていただいています。けれども、この空間に込められた意図をこれだけまとまったかたちで聞くのは、これが初めて。企業のアイデンティティをどう表現し、それをどう世の中につないでいくのか。永野さんのお話には、ぼくらのこれからの「働く」を考えるヒントがたくさん詰まっていました。
みんなが「建てる」なら「建てない」のがソニー

横石 銀座のソニービルがソニーパークに生まれ変わる際、大事にされていたコンセプトが「街に開かれた施設」、そこから導き出されたのが「公園」だったと記憶しています。どうして「街に開かれた施設」で、なぜ「公園」だったのか、改めて伺えますか?
永野さん まず、最初から「公園」ありきだったわけではありません。このプロジェクトのスタートは2013年ですが、もともとソニービルの建て替えプロジェクトとして始まりました。だから、最初に話していたのはどういうビルにするか、何階建てにするか、建築家は誰にしようかといったことで。
けれども、当時は2020年に向けて東京の街でビルの建て替えがどんどん進んでいた時期。その様子を横目で見る中で、ある時ふと、「あれ? ぼくたちが考えていることってほかとあんまり変わらないな」と気づいた瞬間があったんです。
ソニーのアイデンティティのひとつは「人のやらないことをやる」。そこに立ち返るのであれば、何か違うことをやらなければいけないぞ、と。
横石 そこで一度立ち止まるのがいかにもソニーらしいです。
永野さん それで、単純ですが、周りが「建てる」ならば「建てない」のはどうか、となりました。
2016年はソニービルが建って50周年のタイミング。お世話になった銀座への恩返しとして「パブリックなスペースに」というアイデアが出たのも、そこからです。
さらに、ソニービルの歴史を紐解いていくと、実は1966年に建った当時のコンセプトが、まさに「街に開かれた施設」というものだったとわかりました。
ソニー創業者の一人である盛田(昭夫)さんは、数寄屋橋交差点のこの10坪の三角スペースを「銀座の庭」とも呼んでいて。なんだ、当初からパブリックを意識した場所だったのか、と。

こうして導き出されたのが「公園」というアイデアでした。「都会のど真ん中に一私企業が公園を作る」なんて誰も考えないだろうし、ソニービルのもともとのコンセプトも踏襲できる。そして、銀座への恩返しにもなる。
横石 ソニービルはもともとソニー商品のショールーム機能も果たしていました。公園にすることでその機能が失われてしまうわけですが、そこは問題にならなかったのでしょうか?
永野さん アイデアを見直すほどの大きな問題とは考えなかったですね。
そもそも今回のビル建て替えプロジェクトがなぜ始まったかといえば、「新しいソニーのブランドコミュニケーションの場を作る」というのが出発点でした。
50年前のソニーはエレクトロニクス商品しかなかったから、エレクトロニクス商品を置いたショールームがブランドコミュニケーションの最適なインターフェースだったんです。でも、この50年の間にソニーの事業は多角化し、また時代も大きく変化しています。
となると、最適なブランドコミュニケーションのかたちも変わるはず。必ずしもショールームである必要はなく、もっと実験的な場であっていいだろうというのが、ぼくらの認識でした。

テナントではなく「余白」が主役
横石 当然ながら、ソニーは過去に公園を作ったことがないわけですよね。というか、そもそも私企業が公園を作ることが前代未聞です。どうやって作ればいいのかで相当困ったのではないでしょうか?
永野さん そこがソニーという会社の面白いところで。先ほどもお話ししたように、ソニーがこれまでにやってきたのは「人がやらないことをやる」こと。だから、真似をする対象がないのはいつものことです。その分、自分たちで考える。
ソニーのやってきたことを別の言い方で表現するなら、それは「既存のものの再定義」です。
ウォークマンは音楽の聴き方を変えたし、プレイステーションはそれまで子供のトイでしかなかったゲーム機を大人のマシンに変えた。aiboにしてもそうで、人間を助けるためにあったロボットに、ある意味「役に立たなくてもいい」という新たな役割を与えました。
この文脈でいうなら、ぼくらはソニーパークで「都市の公園の再定義」をしているんです。
横石 公園を再定義する仕事なんて、最高に楽しそうです。
永野さん 公園って実にさまざまな使い方をしている人がいるんですよね。お弁当を食べている人もいれば昼寝をしている人もいるし、ボール遊びをしている人も、散歩をしている人も、音楽の練習をしている人もいる。どんな使い方をしても自由なのが公園じゃないですか。
公園と聞いて多くの人がイメージするのは、ある程度のスペースがあり、緑があり、憩いのスペースになっているようなものでしょう。その条件に照らせば、敷地面積が700平米くらいしかないソニーパークは、到底公園にはなれません。
でも、公園があれだけ自由な使い方をできるのは、実は広いからでも、緑があるからでもない。公園を公園たらしめているのは「余白」だと気づいたんです。

横石 余白、ですか。
永野さん 余白があるというのは「こういう使い方をしてください」という決まりごとがなく、どう使うかが使う側に委ねられているということです。
だから、ソニーパークという空間を作るにあたって、ぼくらが最初にデザインしたのも余白でした。
これは旧ソニービルを含めてですが、ほとんどの商業ビルはまずテナントありき。各フロアはすべて使い道が規定されているものです。
今回はその逆。まず余白をデザインし、その隙間に「ちょっとお茶を飲める場所が欲しいね」とか「おみやげを買える場所があったらいいな」というかたちで、お店を誘致していきました。

そうやって作った余白では、来るたびに刺激がある、来るたびに心踊らされる、となるように、1、2か月スパンでプログラムを展開し続けています。
ソニーのアイデンティティには「人のやらないことをやる」とともに「遊び心」というものがありますから、これを体現しようということです。
横石 大規模な展示以外にも毎週末金曜夜にライブイベントをやっていますが、それができるのも「余白が主役」の空間デザインがあってこそということなんですね。

永野さん そうです。なぜ余白を作ることが重要なのか。これは家でも商業施設でも同じですが、実際に動き出せば、人も物も「足し算」でどんどん増えていくじゃないですか。
最初から足し算の発想でいっぱいに埋めてしまっていると、その先のさまざまな使い方を許容できなくなってしまう。ソニービルもまさにそうで、ショールームとして使い道が規定されてしまっているがゆえに、音楽ライブは開催できなかったわけです。
何十年も先のことなんて、基本的には誰にも予測できない。ビジネス環境がどう変化するかなんてわからないし、自分の生活環境やキャリアについても同じことが言えますよね。
そうした不確実性の高い状況では、極力「引き算」の発想でフレキシブルな状態にしておいたほうが、結果的に長くコンフォタブルに使えると思っています。

「開かれている」からこそ知が集まる
横石 おっしゃる通り、オフィスも自宅も、足し算の発想で空間をつくりがちです。我が家では棚をたくさん作ったのですが、油断していたらいつのまにかパンパンにモノが溢れかえっていますし。
ソニーパークでは、そうやって余白をデザインし、余白を運営していく中で、永野さん自身も思いがけなかったようなことは起きたのでしょうか?
永野さん ありますよ、いろいろ。仕事をする人、本を読む人、ご飯を食べる人、昼寝をする人……本当にさまざまな使い方をしていただいているんですが、例えばこの場所のベンチで、一人で宿題をして過ごす小学生の女の子がいて。
最初はただ「ああ、偉いなあ」くらいに思って見ていたんですが、その日だけでなく、その後も何回も同じようにして過ごしているんです。そして、しばらくするとお母さんらしき人がやってきて、一緒に地下鉄の駅のほうに消えていく。
想像するにこの親子は、この場所を待ち合わせに使っていたんですね。お母さんはおそらく働きに出ていて、娘に「お母さんが帰るまでソニーパークのあそこで勉強していなさい。何時になったら迎えにいくから」とやっていたんでしょう。
これは、ぼくの想定していなかった使い方。でも、この親子は気づいたんですよ。ここは無料だし、屋根があるし、スタッフの目もあるから危なくもない。地下鉄に乗るにもすぐです。待ち合わせに最適であることを、誰に言われるまでもなく、この親子は自ら発見したんです。
横石そうやって使う側が発見できたのも、余白がデザインされているからこそ。
永野さん そうなんです。でも、これは使う側にとって理想的なだけではなく、作ったぼくらの側にとっても言えることだと思っていて。
ぼくは常々、アウトプットはインプットの量に比例すると思っているんですが、時間的にも空間的にも、余白がないとインプットはできないじゃないですか。
余白があって初めて、いろいろなアイデアが外から集まってくる。ソニーパークの話で言えば、これだけオープンなスペースがあるからこそ「こんなことがしたい」「こんなことはできないかな?」というアイデアを持った人が向こうからやってきてくれるんです。
そこで「〇〇売り場です」と言ってしまったら、その瞬間に、発想は一気に狭まってしまいます。アイデアを持った人のクリエイティビティを揺さぶらなくなる。
その点で言えば、ここは余白があるだけでなくボーダレスでもあります。見ていただければわかる通り、大階段を降りても扉も何もないですよね?

横石 たしかに雨風や防寒を考えれば扉をつけるのが普通です。
永野さん 地下鉄のコンコースにもボーダレスにつながっていて、そちらは当然ですがソニーの土地ではない。
どこまでがパブリックで、どこからがブライベートなのか、その境目が曖昧に溶け合っているんです。まさに「街に開かれている」。だからこそ、アイデアが入ってきやすいということでもあるのかなと。

横石 そこは納得なんですが、とはいえ、ただ単に開かれた真っ白な箱があればクリエイターやアイデアが集まってくるものでもないですよね?
永野さん おっしゃる通りで、その意味でぼくらが大切にしているのはノイズです。
ソニービル時代の古い躯体を残して新旧を混在させ、あえてラフな空間にしているのは、ノイズを残すためです。人間の認知は面白いもので、ノイズがあると安心感が生まれるんですよね。

横石 ああ、安心感というのはよくわかります。それに、ノイズがあることが「どんなものがあってもいい」という懐の広さとしても映るので、クリエイター側からすると、気軽に提案してみようという気になります。
ノイズを生み出すために新旧を混在させたということですが、旧ソニービルの何を残し、何を捨てるのかの判断はどんな基準で行ったんですか?
永野さん 残したものには明確に共通点がありまして。それは50年前のオリジナルであるということです。
50年の間にはたくさんのものが足し算されてきましたが、そうしたものはすべて捨てて。エレベーターシャフトや壁面のタイルなどの創業当時のものをはじめ、螺旋階段やネオンなどの象徴的なものだけを残しました。
なぜなら、そこにこそ創業者である盛田さんと、建築家の芦原義信さんの思いが込められているからです。それが一番太い。だからこそ残すべきだとぼくらは考えました。地上部には「花びら構造」の一部も残っています。


未来への一歩になっているか
横石 余白をデザインする、ノイズを残すといった考え方は、オフィスづくりや時間の使い方にも応用できる気がします。永野さんが働く上で大切にしていることがほかにもありますか?
永野さん さきほどお伝えした「それが再定義になっているか」に加えて、「世の中への問いかけになっているか」「未来への一歩になっているか」は、どんな仕事をする際にも常に意識しているポイントです。ぼくの美学と言ってもいいと思います。
再定義したところで、真似してくれる人が現れなければ成功とは言えません。ウォークマンにしてもプレイステーションにしても、そのあとに真似をしてくれる人が現れたからこそ、これだけ世の中が変わっていきました。
ソニービルにしてもそうです。銀座の一等地に物を売らずに見せるだけのためにビルを作るというのは、当時まったく新しい考え方でしたが、その後、たくさんのショールームができ、当たり前の概念になりました。
そして、ぼくもまた今回、「街に開かれた施設」という当時のコンセプトを引き継いだわけです。ソニーパークもそうなればいいと思っていて。

ソニーパークは期間限定です。やがて新たなビルが建つ。ぼくが「都市の公園の再定義」として提唱しているのは、その「壊す」と「建てる」の間に余白を作り、数年間だけでも公園にしましょうということなんです。そうすれば都市に緑が生まれるし、リズムが生まれるから。
ここに新たなビルが建つころには、街のどこかでほかのビルで建て替えのための取り壊しが起きているでしょう。その時は、今度はそっちが公園になればいいなと思っていて。
ぼくらの再定義した「都市の公園」は移動するんです。これは代々木公園にも駒沢公園にもできないこと。でも、私企業だったら、それが可能になるんです。
横石 なるほど。移動する公園という思想がちゃんと広がった時に初めて、このプロジェクトは成功だったと言えるのかもしれませんね。そうすれば、さっきの小学生の女の子も、ここにビルが建ったあとも、別の待ち合わせ場所を見つけられる。
永野さん まあ、そのころには彼女は卒業していると思いますけどね(笑)。また別の子がそういう場所を見つけられることになればいいなあと思います。

(施設情報)
施設名: Ginza Sony Park(銀座ソニーパーク)
住所 : 東京都中央区銀座5-3-1
アクセス:東京メトロ各線「銀座駅」B9番出口直結 / JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」中央口 徒歩約5分
開園時間:10:00~20:00
* 地上部は 5:00-24:30 の間、ご自由にお入りいただけます
* パーク内の店舗営業時間はそれぞれ異なります
* 最新情報および営業時間につきましては、下記公式サイトよりご確認ください
休園日:12月31日、1月1日
https://www.ginzasonypark.jp/
* * *
探訪後記 (横石崇・記)
オフィスであれ、家であれ、余白をデザインすることは簡単ではない。
余白自体には、合理性もなければ、機能性もない。何もない空間をつくるには、大いなる勇気と周囲の理解が必要だ。そして、仮に余白をつくったとしても、今度は「何も起こらないかもしれない」という不安と葛藤することにもなるから、なおさら難しい。
でも、それを乗り越えるためのヒントを銀座ソニーパークは教えてくれる。いま都市やオフィスに必要なのは創造性だ。もし、あなたの職場に人やアイデアを呼び込みたいと思うなら、余白の導入を検討してほしい。
余白を信じるものだけが、人を呼び込み、アイデアを呼び込み、未来への問いかけを創造することができるのではないだろうか。

多摩美術大学卒。広告代理店、人材コンサルティング会社を経て、2016年に&Co., Ltd.を設立。ブランド開発や組織開発、空間プロデュースを手がけるプロジェクトプロデューサー。毎年11月に開催するアジア最大規模の働き方の祭典「Tokyo Work Design Week」では7年間で、のべ3万人を動員した。鎌倉のコレクティブオフィス「北条SANCI」支配人。著書『これからの僕らの働き方』(早川書房)、『自己紹介2.0』(KADOKAWA)がある。現在、法政大学キャリアデザイン学部非常勤講師も務める